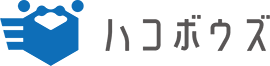運送業界では、長年にわたり人手不足が深刻な課題とされてきました。特に近年、その傾向は加速し「人手不足は当たり前」とまで言われる状況です。
なぜ、人材が集まりにくく、定着しづらいのでしょうか。また、この問題は業界全体にどのような影響を及ぼしているのでしょうか。
この記事では、最新のデータや予測をもとに、運送業界の人手不足の原因や課題を解説します。
さらに、企業が具体的な対策事例も紹介し、業界の現状と今後の展望を探ります。
運送業の人手不足に関するデータ
運送業界では、ドライバー不足が年々深刻化しています。
実際のデータを見てみると、トラック運転者数は1995年をピークに減少を続けており、29歳以下の若年層の就業割合も10%未満と非常に低い水準です。
一方で、40〜59歳のドライバーが全体の58.5%を占めており、高齢化が進んでいる実態が浮き彫りになっています。
さらに、物流業界全体の人手不足データからも、業界の慢性的な労働力不足が明らかです。加えて、EC市場の拡大によって荷物量は増加の一途をたどっています。
物流業界の人手不足に関するデータを見ても、需要と供給のバランスが大きく崩れていることが分かります。
参考:
物流を取り巻く現状について|国土交通省 物流政策課
人材不足の現況について|ヤマトリース
トラック運送業の現状等について|国土交通省
我が国の物流を取り巻く現状と取組状況|経済産業省・国土交通省・農林水産省
2030年におけるドライバー不足状況の予測
ドライバー不足の予測は、今後の物流を考えるうえで非常に重要な指標です。
野村総合研究所の調査によると、2030年度には全国でドライバーが36%不足すると試算されています。特に地方部では40%を超える地域もあり、地域間の格差が一層深刻化する見通しです。
さらに、ドライバーの平均年齢が上昇しており、若年層の就業率の低迷も問題の一因となっています。消費関連貨物の増加に伴い、輸送量の拡大に比例して必要な人手も確保しなければなりません。
加えて、労働時間規制の強化が供給力の低下に拍車をかける形となっています。
2030年におけるドライバー不足は一時的な人材難ではなく、業界構造そのものが問われる課題といえるでしょう。
参考:
2024年以降も深刻化する物流危機|NRI
IoT、ビッグデータ、人工知能の進展による2030年の物流ビジョン報告書|日本ロジスティクス システム協会
迫りくるトラック運転手不足に対する戦略的政策提言|運輸総合研究所
運送業界の人手不足がもたらす影響
もっとも顕著なのが、配送の遅延や配達時間の不安定化です。
限られた人員で多くの荷物をさばく必要があるため、効率が低下し、結果としてサービス品質の低下につながるケースが増えています。
また、過酷な労働環境が離職者の増加を招き、新規採用の難しさを加速させるという悪循環も生じています。
さらに、ドライバー不足の影響はコスト面にも及び、賃金の上昇や燃料価格の高騰と相まって、運賃や物流コストの上昇を引き起こしています。
こうした状況は荷主企業にも波及し、経営への影響も無視できません。運送業の人手不足は、現場だけでなく経済全体に波紋を広げる深刻な問題となっています。
なぜ?運送業での人手不足が「当たり前」となっている原因
運送業の人手不足は、もはや一時的な課題ではなく「当たり前」とされるほど深刻化しています。
ドライバー不足が続く背景には、宅配業者やトラック業界における構造的な問題が関係しています。
ここでは、運送業で人手不足が常態化している主な原因を掘り下げます。
入職する人が少ないから
運送業は「きつい・汚い・危険」といったイメージが定着しており、若者から敬遠されがちです。また、これが業界の印象悪化に拍車をかけています。
さらに、長時間労働や荷役作業の重労働に対して、賃金や福利厚生が見合っていないケースも多く、魅力的な職場と感じにくいのが現実です。
その結果、求職者は他業種に流れやすく、新たな人材が定着しづらい状況が続いています。

離職率が高く、定着しにくいから
運送業界では、離職率の高さが人手不足を常態化させている要因の1つとなっています。
2024年問題によってドライバーの時間外労働が規制され、労働環境の改善が期待される一方で、業務量に対する人手不足はさらに深刻化しています。
実際に、運輸業は全産業と比べて高齢化が進んでおり、若年層の入職率は年々低下。1度就業しても、長時間労働や体力的な負担から離職するケースが多く見られます。
さらに、60歳以上の高齢者の離職率も高く、現場の人材が定着しにくい状況が続いています。
参考:運輸業の労働者をめぐる状況|国土交通省
荷物量の増加に対して人員供給が追いついていないから
EC市場の拡大や消費者ニーズの多様化により、物流業界の荷物量は年々増加しています。
特に、小口配送や即日対応といった細かなニーズが主流となり、配送件数は大幅に伸びていますが、それに対応する人手が確保できていないのが現状です。
荷物が増えても、ドライバーや倉庫スタッフなどの人員は横ばい、もしくは減少傾向にあり、業務負担が一部の従業員に集中しやすくなっています。
その結果、長時間労働やミスの増加といった問題が発生しやすくなり、人材の定着を妨げる要因にもなっています。
ドライバー不足は「嘘」という意見も
確かに、運送業界全体では人材不足が深刻ですが、すべての企業が同じように困っているわけではありません。ドライバー不足の実態は企業ごとに差があります。
なかには、働きやすい環境づくりや業務効率の改善に取り組み、安定した人材確保に成功している企業も存在します。
つまり、問題は単なる人手不足ではなく、業務の無駄や人材配置の偏りにあるケースも多いのです。
例えば、非効率な配車や過剰な荷待ち時間が慢性的な残業を生み、それが離職を招いている事例も見受けられます。
人手が足りないと言われる背景には、業界構造だけでなく、企業ごとの取り組み姿勢の違いも大きく影響しているといえるでしょう。
運送業の人手不足解消の対策
深刻化する運送業の人手不足に対し、企業や国がさまざまな解決策を進めています。
ここからは、具体的にどのような対策が求められているのかをみていきましょう。
労働条件の改善
多くの運送会社では、ドライバーの負担を軽減するために労働条件を見直しています。例えば、長時間労働の是正に向けて、運行管理のデジタル化やシフト勤務制度の導入が挙げられます。
また、休憩スペースの整備や福利厚生の充実も、働く人の安心感につながる重要な施策です。
さらに、研修制度を整えることで業務への不安を軽減し、定着率の向上を図る企業も増えています。
国や自治体レベルでは、時間外労働の上限規制といった法整備が進められており、ドライバーの健康と生活を守るための支援も拡大しています。

デジタル技術・ITによる業務効率化
業務の効率化を進めるうえで、デジタル技術やITツールの導入は有効な手段です。
特に、人手不足が深刻化する中で限られた人員で安定した物流を維持するためには、ITの力も活用することが重要です。
以下は、実際に導入されている取り組みの例です。
| 取り組み | 効果 |
|---|---|
| 配車システムやルート最適化ツールの導入 | 配送ルートを効率化し、無駄な走行時間や燃料の削減、ドライバーの負担を軽減 |
| 運行記録の自動管理システムの活用 | 手書きの運行記録をデジタル化して記録ミスを防ぎ、事務作業の負担を軽減 |
| クラウドサービスを活用した荷主との情報共有 | 配送状況や納品時間をリアルタイムで共有でき、コミュニケーション効率化と信頼性向上 |
| スマートフォンを使った勤怠管理システムの導入 | 出退勤の記録をスマホで簡単に行い、時間管理がしやすくなり、ペーパーレス化推進 |
国や自治体でも、これらのIT導入を支援する補助金制度が整備されており、中小規模の運送会社でも導入しやすい環境が整いつつあります。
若年層・女性ドライバーの採用促進
人手不足の解消には、これまで十分に活用されてこなかった層へのアプローチが効果的です。
特に、若年層と女性の採用促進は、将来的な担い手を増やすうえで重要な施策といえます。
近年では、高校生向けの業界紹介パンフレットやインターン制度を活用し、職業としての魅力を伝える取り組みが広がっています。
また、女性が安心して働けるよう、トイレや更衣室の整備、軽自動車やワゴン車の導入なども進んでいます。
さらに、育児支援制度や短時間勤務制度を導入する企業も増えており、ライフスタイルに応じた働き方が選べる環境が整いつつあります。
行政もこうした動きを後押ししており、助成金や研修プログラムを通じて、多様な人材の活躍を支援しています。
参考:
トラック運送業における人材確保のためのパンフレット・好事例集について|国土交通省
パート・アルバイト採用|ヤマト運輸
運送業界の企業における人手不足(ドライバー不足)への対策事例
人手不足の課題に対し、現場ではどのような工夫が行われているのでしょうか。
ここでは、実際の成功事例をいくつか取り上げ、解決へのヒントを探ります。
株式会社ジャスト・カーゴ(北海道石狩市):労働時間短縮と教育改革で定着率を向上
株式会社ジャスト・カーゴでは、ドライバーの働きやすさを重視した取り組みを進め、定着率の向上に成果を上げています。
特に注力しているのが、労働時間の短縮と教育体制の見直しです。高速道路の利用やICT機器の活用によって拘束時間を削減し、ドライバーが無理なく働ける環境を整えています。
また、社内教育の内容を見直しています。
以前は会社主導で細かいマニュアルを作成していましたが、押し付けの方法では効果が見られませんでした。そこで、会社からは重要なポイントだけを示し、細かいルールはドライバー自身で決めるように改めました。
さらに、研修にディスカッションを取り入れることで、研修後にはドライバー同士が相談し合い、仕事をシェアするようになりました。
このような取り組みが、より自主的で協力的な働き方を促進しています。
有限会社石原運輸(北海道小樽市):高齢者・女性も活躍できる多様な働き方を実現
有限会社石原運輸は、高齢者や女性など幅広い人材が安心して働ける環境づくりに力を入れている企業です。
特に、ライフスタイルに合わせた就業形態の導入や1泊運行を極力断る取り組みなど、体力的な負担や労働時間に配慮した柔軟な働き方を推進しています。
また、自社で整備士を雇用することで、ドライバーが整備に時間を取られず、本来の業務に専念できる環境を構築。
さらに、荷積み・荷下ろしはお客様に依頼することで、ドライバーの重労働を軽減しています。
社内教育にも力を入れており、外部講師による管理者研修や高齢者ドライバーの再教育を実施。加えて、2009年から全車両にデジタルタコグラフを導入し、運転データの数値化・見える化を実現。ICT機器の活用により、燃費が約1km/h向上し、約30%の削減率を達成しました。
これらの取り組みにより、ドライバーの負担を軽減し、環境にも配慮した働きやすい職場環境を実現しています。
株式会社丸山運送(宮城県仙台市):ステップアップ制度と社内文化づくりで採用力強化
株式会社丸山運送は、ドライバーの採用と定着を両立させるために、明確なステップアップ制度と前向きに働ける職場環境に力を入れています。
未経験者が入社後も安心して成長できるよう、業務に応じた等級制度を導入し、努力や実績を正当に評価する仕組みを整えています。
また、社内教育にも力を入れており、新規ドライバーには机上研修・初任研修に加え、本人が「1人で大丈夫」と感じるまで同乗研修を実施。
運転時間・休憩時間・運行速度のコンプライアンス遵守も徹底し、安全管理を徹底しています。
また、朝礼では「褒めワーク」を継続的に実施し、否定する文化をなくすことで、職場の雰囲気が大幅に改善されました。社員同士が支え合う風土が根づき、より働きやすい環境が整っています。
さらに、東日本大震災ではおよそ25台のトラックと50台のトレーラーが流される被害を受けながらも業務を継続。その経験を活かし、強い組織づくりを推進しています。
参考:トラックドライバーの採用・定着に向けた取組事例・ポイントを紹介します|国土交通省
ハコボウズのキャリア相談で採用活動を効率化◎
運送業界に特化した転職支援サービス「ハコボウズ」は、ドライバーを採用したい企業と職場を探している求職者の間に立ち、効率的なマッチングを実現しています。
利用者1人ひとりの希望やスキルを丁寧にヒアリングし、それに合った求人を紹介する仕組みのため、ミスマッチが起こりにくいのが特長です。
企業側にとっても、業界に精通したエージェントが条件交渉や面接日程の調整を代行してくれるため、採用業務の負担を大きく軽減できます。
また、ドライバーには自己PRの作成や面接対策のサポートも用意されており、不安なく応募できる環境が整っています。
双方にとってメリットの大きいサービスとなっていますので、ぜひご活用ください。