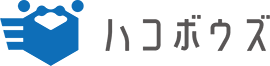「優良な軽貨物ドライバーの求人を探したい」「効率的にドライバーを採用する方法がわからない」などと悩んでいませんか。
軽貨物ドライバーの採用は、多くの企業にとって重要な課題です。
本記事では、「ホワイト物流推進運動」を背景とした軽貨物業界の求人の重要性について詳しく解説します。
ホワイト物流とは
「ホワイト物流」とは、物流業界全体で労働環境を改善し、輸送の効率化を高めるための取り組みです。
2019年に国土交通省が「ホワイト物流推進運動」として開始して以来、多くの企業が賛同し、ドライバー不足の解消や業務の効率化を進めています。
本運動が始まってから企業は安定した物流網を確保し、持続可能な経営の実現にもつながっています。
出典:
「ホワイト物流」推進運動について|「ホワイト物流」推進運動ポータルサイト
「ホワイト物流」推進運動のご案内と参加のお願い|国土交通省・経済産業省・農林水産省
ホワイト物流推進運動の目的
ホワイト物流推進運動の目的は、物流業界の持続的な成長と社会的な課題解決を両立させることにあります。
特に、深刻なドライバー不足や非効率な輸送体系を改善し、業界全体の労働環境を整えることを重視しています。
具体的には、長時間労働や過度な付帯作業といった課題を解消し、ドライバーが安心して働ける環境をつくることが重要です。そのため、運行管理の効率化や荷待ち時間の短縮、積載効率の向上といった対策が推奨されています。
また、これらの取り組みによって輸送コストの削減やドライバーの定着率向上が期待されています。
結果として、ホワイト物流推進運動では物流業界における生産性の向上と環境負荷の低減が同時に実現されることを目指しています。
ホワイト物流推進運動は、単なる効率化ではなく、働く人と企業の双方にメリットをもたらす役割を担っているといえるでしょう。
グリーン物流との違い
ホワイト物流とグリーン物流は、いずれも持続可能な物流を目指す取り組みですが、重視するポイントが異なります。
ホワイト物流は、労働環境の改善や物流の効率化に焦点を当てており、ドライバー不足の解消や過重労働の防止、働きやすい環境づくりが主な目的です。
一方、グリーン物流は環境負荷の削減を重点にしています。二酸化炭素の排出量を減らすためのエコドライブの導入や再生可能エネルギーの活用など、環境保護を目的とした取り組みが進められています。
出典:グリーン物流の推進|国土交通省
ホワイト物流推進運動の賛同企業
ホワイト物流推進運動には、国内外の多くの企業が賛同しています。2025年2月10日時点で、賛同企業数は3,074社です。
ホワイト物流には、食品・飲料・製造・小売・流通など、さまざまな業界の企業が参加しています。代表的な賛同企業として、以下の企業が挙げられます。
- 【食品・飲料】サントリーホールディングス株式会社・キリンビバレッジ株式会社・株式会社伊藤園など
- 【製造業】トヨタ自動車株式会社・東レ株式会社・三菱ケミカル株式会社・住友化学株式会社・レンゴー株式会社・株式会社リコー・株式会社LIXILなど
- 【小売・流通】株式会社セブンーイレブン・ジャパン・株式会社サンドラッグ・ヤマト運輸株式会社・佐川急便株式会社・日立建機ロジテック株式会社など
出典:賛同企業リスト|「ホワイト物流」推進運動ポータルサイト
ホワイト物流推進運動の背景
ホワイト物流推進運動が始まった背景には、物流業界全体が直面するさまざまな課題があります。
この章では、運動が必要とされた主な理由について詳しく説明します。
ドライバー不足の深刻化
物流業界で最も大きな課題の1つが、ドライバー不足の深刻化です。
近年、ドライバーの高齢化が進み引退する人が増える一方で、若年層の就業希望者は減少しています。
その結果、荷物の輸送遅延や業務負担の増加など、現場にさまざまな影響が出ているのです。
このような問題により、安定した輸送体制の維持が困難になっているのが現状です。
課題の多い労働環境
物流業界では、長時間労働や荷待ち時間の長さ、付帯作業の多さが問題視されています。
特に、過酷な労働条件が原因でドライバーが業界を離れるケースが多く、これが定着率の低下を招いています。
具体的には、荷物の積み下ろし作業や運行計画の不備によって、荷物輸送が予定よりも大幅に遅れるケースが日常的に発生しています。
こうした現状が、ドライバーの肉体的・精神的負担をさらに増加させています。
効率的な物流の必要性
物流業界では、これまで非効率な輸送体系が大きな課題とされてきました。
積載効率の低下や輸送ルートの不備、荷待ち時間の増加などがその主な要因です。
このような状態が続けば、企業のコスト増加にとどまらず、業界全体の生産性も低下し、持続可能な物流の実現が難しくなります。
例えば、荷待ち時間が長くなることでドライバーの拘束時間が増加し、労働負担が重くなるのも深刻な問題です。
さらに、従来の物流体制は需要の変化に柔軟に対応できておらず、繁忙期には一時的に輸送網が過剰負担を受ける一方で、閑散期には人員を持て余している会社も少なくありません。
出典:「ホワイト物流」推進運動のご案内と参加のお願い|国土交通省・経済産業省・農林水産省
2024年問題への直面も背景の1つ
2024年問題とは、働き方改革関連法の施行に伴い、トラックドライバーを含む運送業界に対する労働時間の上限規制が強化されることで発生するさまざまな問題です。
この規制により、ドライバーの1日や1週間あたりの労働時間が厳しく制限されるため、これまでの長時間労働を前提とした輸送計画の見直しが迫られています。
この影響で、現在の輸送量が維持できなくなる可能性が高まり、企業間の荷物の受け渡しや納品スケジュールに遅れが生じる懸念があります。
また、すでにドライバー不足が続いている中での規制強化は、さらに人手不足を引き起こす可能性もあるでしょう。

ホワイト物流のメリット
ホワイト物流推進運動は、企業が抱える課題を解決するだけでなく、さまざまなメリットをもたらす取り組みです。
それぞれのメリットについて、以下で詳しく紹介します。
ドライバーの定着率が上がる
ホワイト物流推進運動に参加することで、ドライバーの定着率が向上するメリットがあります。
その理由は、労働環境が改善され、ドライバーが長期間安心して働ける職場が提供されることにつながるからです。
従来の物流業界では、長時間労働や過剰な付帯作業が原因で離職率が高いという問題がありました。しかし、これらの課題を解消する取り組みが進められています。
例えば、荷待ち時間の短縮や積載計画の最適化を通して、ドライバーの負担が軽減される事例が増えています。具体的には、無駄な待機や深夜運行が減り、規則正しいスケジュールで稼働できることで、働きやすい環境が整います。
結果として、離職のリスクが低下し、長期的な人材確保がしやすくなるでしょう。
業務が効率化できる
ホワイト物流の導入により、物流業務全般の効率化が実現できます。
そのためには、荷主と運送業者の連携強化やIT技術を活用した運行管理が必要不可欠です。
非効率な運行計画や空車での移動が減ることで、輸送コストの削減にもつながります。
具体的な事例としては、AIを活用した積載率の最適化や荷物のリアルタイム追跡によるスムーズな配送管理が挙げられます。
また、ドライバーの負担が軽減されることで突発的なトラブルや遅延の発生も減少し、業務の流れがより円滑になるでしょう。
企業イメージが向上する
ホワイト物流の取り組みは、社会的に見ても企業イメージの向上につながるでしょう。
働きやすい職場環境の整備やドライバーの労働条件改善は、企業の社会的責任(CSR)を果たす一環として評価されるためです。
特に、大手企業がホワイト物流推進運動への参加を公表することで、取引先や顧客からの信頼が高まり、ビジネス上で優位になる場面もあるでしょう。
また、環境負荷の軽減や持続可能な物流の実現が評価されることにより、採用活動にも好影響を与えます。
求職者が安心して応募できる環境が整えば、優秀な人材を確保できるようになります。
ホワイト物流は単に業務改善を目的とするだけでなく、社会的な信頼や評価を得るための重要な要素でもあるのです。
ホワイト物流のデメリット・課題
ホワイト物流推進運動には多くのメリットがある一方で、企業が取り組む際にはいくつかのデメリットや課題が生じる可能性があります。
ホワイト物流の取り組みには、積載効率の向上やITを活用した運行管理システムの導入が求められますが、これらには一定の初期費用がかかります。中小企業にとっては、この費用負担が重く感じられる場合もあるでしょう。
また、新しいシステムや業務フローを現場に浸透させるための教育や研修が必要となり、短期的な運用負担が増えることも懸念されています。
さらに、ホワイト物流の取り組みには荷主や運送業者、倉庫業者など、複数の関係者が関わります。それぞれの立場によって利害が異なるため、効率化に向けた調整がスムーズに進まないこともあるはずです。
加えて、既存の業務フローとの整合性の問題も課題の1つです。特に、従来の慣習に基づく決まりごとが多い現場では、新しい仕組みの導入に対する抵抗が発生することがあります。
そのため、段階的な導入や試験運用によって徐々に改善を図るアプローチが有効です。
これらの課題を克服するためには、政府の補助金や助成金の活用、外部専門家の支援を受けるなど、柔軟な対応が必要だといえます。
ホワイト物流推進運動への参加手順
ホワイト物流推進運動に参加するためには、以下の手順で進める必要があります。
1)自主行動宣言の必須項目への賛同表明
まず、ホワイト物流推進運動の趣旨に賛同し、「自主行動宣言」の必須項目に同意することが求められます。必須項目は、以下の3点です。
- 取組方針:物流を安定的に確保することを経営課題とし、効率的な物流と働き方改革を目指します。そのために、取引先や物流事業者と協力しながら、改善に取り組みます。
- 法令遵守への配慮:物流事業者が労働関係法令・貨物自動車運送事業関係法令を遵守できるよう、契約内容や運送内容の見直しを適切に行い、法令違反が生じないよう配慮します。
- 契約内容の明確化・遵守:運送および荷役、検品などの業務内容を明確にし、関係者と協力しながら契約を遵守します。
2)自社でさらに取り組む項目を選定
必須項目への同意に加えて、自社でさらに取り組むべき項目を選定する必要があります。
項目は、公式に示されている「推奨項目リスト」から選ぶのが基本です。
このリストには、運送内容や作業工程の見直しや効率的な積載管理の導入、ITを活用した運行管理など、物流全体の効率化と労働環境の改善につながるさまざまな施策が含まれています。
項目を選定する際には、自社の課題やリソースを考慮し、段階的に実行できるものから目星をつけていきましょう。
また、選んだ項目は計画的に導入し、定期的に見直すことで持続的に改善していくことができます。
推奨項目リスト
ホワイト物流推進運動では、以下のような具体的な施策が推奨されています。
- 輸送内容の最適化:積載効率の向上・共同配送の活用
- 作業の合理化:荷待ち時間の短縮・付帯作業の軽減
- IT技術の活用:AI・IoTによる運行管理システムの導入
- 契約内容の見直し:透明な契約内容の設定と遵守
- 労働環境の改善:ドライバーの拘束時間の削減・適切な休息の確保
3)事務局に提出
ホワイト物流推進運動に正式に参加するためには、「ホワイト物流」推進運動ポータルサイトから「自主行動宣言様式フォーマット」をダウンロードし、自社の自主行動宣言を作成する必要があります。
作成後は、提出用フォームを通じて、ホワイト物流推進運動の事務局に提出します。これで、正式に運動へ参加でき、各種サポートや情報提供を受けられます。
なお、参加後も継続的な改善や進捗状況の報告が求められるため、実効性のある取り組みを進めていくことが重要です。
出典:「ホワイト物流」推進運動への参加手順|「ホワイト物流」推進運動ポータルサイト
ホワイト物流の取り組み事例
ホワイト物流推進運動では、物流の効率化とドライバーの労働環境改善を目指し、さまざまな取り組みが行われています。ここでは具体的な事例を紹介します。
集荷と幹線輸送のドライバー分離の事例
佐賀県の運送会社では従来、集荷から幹線輸送、そして配送までを1人のドライバーが担当するケースが一般的でしたが、この方法ではドライバーの拘束時間が長くなり、労働負担が増大する傾向がありました。
この問題を改善するため、集荷と幹線輸送の工程を分け、それぞれ別のドライバーが担当する体制を導入しています。
具体的には、集荷ドライバーが荷物を中継拠点まで運び、そこから別の幹線輸送ドライバーが目的地まで輸送する方法を採用しました。
この分業体制により、各ドライバーの拘束時間が短縮され、労働環境が改善されています。
参考:集荷と幹線輸送のドライバー分離による拘束時間削減 佐賀県|厚生労働省 労働基準局 労働条件政策課 国土交通省 自動車局 貨物課 公益社団法人 全日本トラック協会
タイムスケジュールの明確化の事例
ドライバーの拘束時間を削減し、物流の効率化を図るために、発荷主と運送事業者が連携してタイムスケジュールを明確化した愛知県の運送事業者の事例があります。
従来の現場では、荷物の準備や積み込み作業が不明確だったため、ドライバーの待機時間が長くなり、現場の効率が低下していました。
この課題を解決するため、関係者が協力してタイムスケジュールを可視化することに。
具体的には、発荷主の工事主任と運送事業者の輸送リーダーが連携し、当日のローディング時間を明確にした「タイムスケジュール(予定)」を共有する取り組みました。
この取り組みにより、次のような具体的な成果が得られています。
- ドライバーの無駄な待機時間が削減され、拘束時間が大幅に短縮
- 工事主任が積荷の進行状況を管理し、現場の調整がスムーズに
- スケジュール通りに作業が進み、物流全体の効率が向上
さらに、現場関係者が継続的にフォローアップすることで、改善の定着とさらなる効率化が進んでいます。
出典:『タイムスケジュール』明確化による現場意識改革 愛知県|厚生労働省 労働基準局 労働条件政策課 国土交通省 自動車局 貨物課 公益社団法人 全日本トラック協会
短距離輸送におけるモーダルシフトの事例
モーダルシフトとは、輸送手段をトラックから鉄道や船舶などに切り替えることで、環境負荷の低減や労働環境の改善を図る取り組みです。
一般的に長距離輸送で採用されるケースが多く見られますが、短距離輸送においても効果的な事例があります。
例えば、和歌山県の企業では、トラックによる輸送から内航海運に切り替えることでドライバーの拘束時間の削減に成功しました。
具体的には、和歌山港~神戸・大阪港への輸送をトラックから船舶に変更し、ドライバーは港までの短距離輸送を担当することにし、労働時間の短縮と輸送コスト、CO2排出量の削減ができています。
出典:短距離輸送におけるモーダルシフトによる運転者の拘束時間削減 和歌山県|厚生労働省 労働基準局 労働条件政策課 国土交通省 自動車局 貨物課 公益社団法人 全日本トラック協会
【FAQ】ホワイト物流に関するよくある質問
ここでは、企業がホワイト物流推進運動への参加を検討する際によく寄せられる質問を紹介します。
賛同企業になることで補助金や助成金がもらえる?
ホワイト物流推進運動に賛同することで、各自治体による補助金や助成金を受けられる場合があります。
例えば、熊本県天草市では「ホワイト物流推進事業」に関する支援が行われており、物流効率化への取り組みに対して1台あたり15,000〜50,000円が補助されます。
また、鳥取県でも「ホワイト物流推進事業補助金」を設けており、運送事業者や荷主が行う効率化施策に対して経済的な支援が用意されています。
さらに、国土交通省の取り組みでは中継輸送やモーダルシフトといった具体的な施策に対する助成も行われており、ホワイト物流推進運動に賛同することで、ほかの補助金申請時にも有利に働くでしょう。
このように、ホワイト物流推進運動に参加することで直接的な補助金の利用だけでなく、ほかの施策や制度の活用時にもメリットがある場合があります。
自治体ごとに制度や条件が異なるため、賛同企業として参加を決めた際には自治体の公式窓口や関連情報をしっかりと確認することが重要です。
出典:
熊本県におけるホワイト物流推進事業の実施について | 公益社団法人 熊本県トラック協会
【熊本県】ホワイト物流推進支援金の案内(貨物運送事業者向け)|天草市
【募集終了】ホワイト物流推進事業補助金のご案内|鳥取県
モーダルシフト等推進事業|国土交通省
ホワイト物流に参加できるのはいつからいつまで?
ホワイト物流推進運動は、2019年に国土交通省や経済産業省、農林水産省などが中心となって開始されました。
当初、この運動はトラック運転者の時間外労働の上限規制が適用される2024年3月末までを目途としていましたが、2025年2月現在、ホワイト物流推進運動は継続して実施されています。
公式ポータルサイトも引き続き運営されており、企業の自主行動宣言の提出や情報共有の場として機能しています。
ホワイト物流の「集いの場」とは?
「集いの場」とは、ホワイト物流推進運動に賛同する企業が参加できる専用のオンラインプラットフォームです。
ここでは、情報交換や意見共有を通じて、参加企業が物流の課題解決や業務改善を目指しています。
集いの場は、企業同士の連携を強化し、現場の課題を解決するために設けられたものです。利用には、事前に発行される専用のIDとパスワードが必要です。
「集いの場」でできることは、以下のとおりです。
- 企業が抱える物流の課題や取り組み状況を共有できる
- 他社の成功事例やノウハウを参考にできる
- 物流効率化のアイデアや施策について意見ができる
- 課題解決策のための具体的なヒントが得られる
また、「集いの場」では、イベント情報やセミナーの案内も掲載されており、物流業界の最新動向を把握するのにも役立ちます。ほかの企業からフィードバックを得ることで、自社の取り組みをより効果的に進められるでしょう。
出典:集いの場|「ホワイト物流」推進運動ポータルサイト
優良な運送会社の軽貨物求人を探すなら「ハコボウズ」
ホワイト物流推進運動は、物流業界の労働環境を改善し、効率的な輸送体制を構築するために、多くの企業が取り組んでいる重要な活動です。
特に、ドライバー不足の深刻化や働き方改革への対応が求められる中、優良な運送会社の求人探しがますます重要になっています。
一方で、企業にとっても適切な人材を迅速に確保することが、物流業務の安定に直結する大きな課題です。
こうした課題を解決するために役立つのが「ハコボウズ」です。
「ハコボウズ」は軽貨物運送業に特化した求人サイトで、初期費用や掲載費用が一切かからない完全成果報酬型の料金体系を採用しています。
そのため、無駄なコストを抑えながら、効率的な採用活動が可能です。
「ハコボウズ」は、掲載件数や期間に制限がなく、最短10分で求人情報を掲載できるため、迅速な人材確保が期待できます。
また、各種求人検索エンジンとの連携しているため、高い集客力があり、多くの求職者に情報を届けられます。
「ハコボウズ」のメリットを活用して、自社の採用活動をさらに効果的に進めてみてはいかがでしょうか。