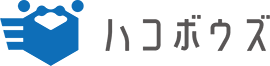グーグルマップは、目的地検索の精度が高く、無料で使えるカーナビアプリとして多くのユーザーに利用されています。
しかし、個人の移動だけでなく「配送業務でも本当に使えるのか?」と気になる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、グーグルマップのメリット・デメリットを整理し、配送での利用に向いている人の特徴やルート作成の手順も紹介します。
さらに、グーグルマップ以外の配送ルート最適化アプリについても解説します。小規模な配送業者や個人ドライバーで、グーグルマップを配送業務に取り入れたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
グーグルマップ(Google map)で配送ルートを作成できる?
グーグルマップでも配送ルートの作成は可能です。
出発地と複数の目的地を登録することで、ルートが地図上に表示されるため効率的に配達ルートを計画できます。
スマートフォンさえあればすぐに使える上、無料で利用できる点も大きな魅力です。
ただし、配達専用に設計された業務用アプリと比べると件数が多い配達やルートの自動最適化には対応していないため、使い方に工夫が必要です。
グーグルマップ(Google map)で配送ルートを作成するメリット
グーグルマップには、配送業務をサポートする便利な機能があります。ここでは、代表的な3つのメリットをご紹介します。
複数の経由地を簡単にルート化できる
グーグルマップでは、出発地に加えて最大9か所までの配送先を「経由地」として入力できます。
出発地はJ欄、経由地はA〜I欄にそれぞれ登録され、全体の配送ルートがひと目で把握できる点が特徴です。
また、スマートフォンでは経由地を長押しすることで順番を入れ替えられ、効率的な回り方を簡単に調整できます。
一括でルートが表示されるため、土地勘がないエリアでも道順のイメージがつきやすく、事前の計画や確認にも役立ちます。
リアルタイムの交通状況が反映される
グーグルマップは、グーグルの膨大なデータベースと位置情報の仕組みを活用しているアプリです。そのため渋滞や事故、工事などの交通情報をリアルタイムで反映します。
これにより、混雑を避けたルートが自動で提示され、無駄な遅れを最小限に抑えた配送が可能になります。
また、通行止めの情報や道路の工事状況も迅速に更新されるため、突発的なルート変更にも柔軟に対応できます。
さらに、衛星写真やストリートビューの機能を使えば、初めての場所でも安心して走行できる点も魅力です。
目的地ごとの所要時間や距離がすぐわかる
グーグルマップでは、目的地ごとの所要時間や距離を簡単に確認できます。
スマートフォンの場合、画面下部にある情報欄を上にスワイプすると、詳細画面が全体に表示されます。
すると各目的地までの所要時間や距離、道順が一覧で確認できます。
さらに、グーグルマップに表示される道順には、写真付きのビジュアルガイドが含まれています。よりリアルに道順を確認できるため、初めてのエリアでもスムーズに配送できるでしょう。
グーグルマップ(Google map)で配送ルートを作成するデメリット・注意点
グーグルマップは無料で使えて便利な反面、配送業務においては機能面でいくつかの制限があります。
ここからは、利用時に注意しておきたい3つのポイントを紹介します。
配送先は最大10か所までしか設定できない
グーグルマップのスマートフォンアプリでは、出発地を含めてルート上に登録できる地点は最大10か所までに限られています。
つまり、配送先として設定できる「経由地」は最大9か所までということです。
1日に20〜100件もの配達をこなすような宅配業務では、すべての目的地を1度に登録できないため、ルートを何度も分けて作成しなければなりません。
「配送先に到着して荷物を渡し、その地点のルートが不要になったら次のルートを新たに作成する」という作業の繰り返しが必要になり、手間や時間がかかってしまいます。
最短ルートを自動で並び替える機能がない
グーグルマップでは配送先を複数入力してルートを作成できます。
しかし「どの順番で回るのが最短か」を自動で並び替えてくれる機能(ルート最適化機能)は搭載されていません。
そのため、どの順番で配送するのが効率的かはドライバー自身が判断する必要があります。
配送に慣れている人であれば、最短ルートを自分で考えて設定することにもある程度対応できるでしょう。しかし、初心者にとってはルートの組み立て自体が負担になる場合もあります。
効率的に回る順番を考えるには、土地勘や経験、あるいはほかの補助ツールの活用も必要になるでしょう。
配達先は1件ずつ手入力が必要
グーグルマップで配送ルートを作成する際は、配達先の住所を1件ずつ手入力する必要があります。
件数が多くなると、入力作業に時間と手間を要する点が大きな負担となるでしょう。
一括で住所を登録する方法として「API(エーピーアイ)」という地図とほかのシステムを連携させる技術もあります。ただし活用するには専門的な知識や開発環境が必要です。
仮に外部に開発を依頼する場合でも費用が発生するため、個人ドライバーにとっては現実的な選択肢とは言い難いのが実情です。
技術面やコスト面の負担が大きいため、日常業務に取り入れるには登録の手間も含めて慎重に検討したほうがよいでしょう。
グーグルマップ(Google map)で配送ルートを作成する方法
ここからは、グーグルマップを使って実際に配送ルートを作成する手順を解説します。
操作は全部で5ステップ。
順を追って、それぞれのステップを詳しくみていきましょう。
- 出発地と最初の目的地を入力する
- 経由地(配送先)を追加する
- 配送ルートを確認し、移動手段を選ぶ
- 必要に応じてルートを並び替える
- ナビを開始して配送スタート
1)出発地と最初の目的地を入力する
まず、グーグルマップの検索バーに最初の配送先を入力しましょう。
出発地は現在地のほか、地図上からの選択や住所の直接入力も可能です。情報を入力すると、出発地から目的地までのルートが自動的に表示されます。
2)経由地(配送先)を追加する
ルートが表示されたら、画面右上の「︙(3点リーダー)」をタップし、「経由地を編集」を選びます。
次に、配送先を順に追加しましょう。スマートフォンでは最大で9か所までの経由地を設定できます。入力欄はA〜Iまであり、すべての配送先をここに登録します。
3)配送ルートを確認し、移動手段を選ぶ
すべての配送先を入力すると、出発地から目的地までの合計移動時間が自動で表示されます。
内容を確認したら「完了」をタップしましょう。
次に、車・電車・徒歩などの移動手段を選びますが、配送業務の場合は「車」を選ぶのが一般的です。
あわせて「移動オプション」から、高速道路や有料道路を避ける設定も行えます。
状況に応じてルートをカスタマイズしましょう。
4)必要に応じてルートを並び替える
グーグルマップには、経由地を自動で最短ルートに並び替える機能がありません。そのため、配送先を回る順番はドライバー自身で調整する必要があります。
ルートを並び替えるには、画面右上の「︙(3点リーダー)」をタップし「経由地を編集」を選択します。
A〜I欄に表示されている配送先の中から、並び替えたい地点を長押しして上下にドラッグすることで順番を自由に変更できます。
効率的な配送を行うためには、この手動での調整が重要です。
5)ナビを開始して配送スタート
「開始」をタップすると、ナビゲーションがスタートします。
スマートフォンの画面下部には、最初の目的地までの所要時間・距離・到着予想時刻が表示され、状況がひと目で把握できます。
音声案内付きナビをONにすれば、運転中でも視線を大きく外すことなく、スムーズにルートを確認できるので安心です。
グーグルマップ(Google map)で配送ルートを作成するのに向いている人
グーグルマップは誰でも無料で使える上、操作も直感的でわかりやすいのが魅力です。
特に、以下のようなケースに当てはまる人には使いやすいツールといえるでしょう。
- 1日10件以内の短距離・中規模の配送を行う人
- 無料のルート作成ツールを活用したい人
- 委託会社などから配送ルート管理アプリが提供されていない人
- 単発案件やスポット便が中心の人
ただし、1日に100件近く配るような業務や効率を最大化するルートを自動で組みたい人には物足りない場面もあります。
こうした場合は、専用のルート最適化ツールの導入を検討するほうが現実的です。
グーグルマップ(Google map)以外の配送ルートアプリ
グーグルマップは広く利用されているルート作成ツールですが、配送業務に特化した専門的なルート最適化アプリも多数存在します。
ここからは、グーグルマップ以外の主要な配送ルートアプリについて詳しく紹介します。

配達NAVITIME
配達NAVITIMEは、ゼンリン住宅地図を搭載したルート作成アプリで、建物名や表札まで地図上で確認できるのが特長です。
階数ごとのテナント名まで表示できるため、マンションやビル内の配達先でも迷いにくく、正確な住所特定が求められる現場で心強い存在です。
伝票のカメラ読み取り機能や建物名・テナント名による検索にも対応しており、住所入力の手間を大幅に削減できます。
配達先ごとの時間帯指定や置き配の場所なども事前に登録可能で、自動的に効率的な順番に並び替えてルートを作成してくれます。
さらに、駐車禁止エリアや進入禁止箇所も地図上に表示されるため安心です。
利用プランは無料とプレミアムコースの2種類。
プレミアムでは、手書きで自分だけのルートメモを残せる「My宅配マップ」など、便利な機能が充実しています。
料金は税込みで月額2,300円、年額は20,000〜22,800円です。
出典:
配達NAVITIME|NAVITIME
『配達NAVITIME』、手書きで自分だけの地図を作れる「My宅配マップ」提供開始|NAVITIME
GODOOR
GODOORの運営は株式会社ゼンリンの関係会社「ゼンリンデータコム」で、公式アプリならではの使いやすさが魅力です。
地図上では、表札や建物名まで確認できる「ゼンリン住宅地図」が見放題。配達時間帯や不在・再配達・集荷の情報も「荷物ピン」として表示されるため、状況をひと目で把握できます。
荷物リストでは、残り・不在・完了などの件数をステータス別に確認でき、「メモ機能」では置き配場所や在宅時間などの情報も記録可能です。
また、荷物のサイズや色、種類も登録できるため誤配の防止にもつながります。
最短ルートを音声で案内するナビ機能も搭載され、現場での使いやすさにも配慮しています。
すべての機能は30日間無料で試せるほか、月額1,300〜1,800円、または年額13,000円で利用できます。
出典:GODOOR配達アプリ|GODOOR

TODOCUサポーター
TODOCUサポーターは、配達業務に特化したドライバー支援アプリです。
荷物の登録は「無料プラン」でも利用可能で、累計1,000件まで登録できます。
基本的な機能が揃った「ノーマルプラン」は月額880円で利用可能です。「プロプラン」(月額1,600円)では、業界最速の表示スピードを誇るゼンリン住宅地図に加え、詳細な住所検索、経路表示、建物情報や建物の入口表示といったプロ向けの機能がすべて利用できます。
初回は有料会員限定機能も1カ月無料で体験できるため、導入前に試せる点も安心です。
特にユニークなのが、アプリ上からワンタップで受取人にSMSを送り不在かどうかを事前に確認できる機能です。
再配達の手間を減らし、効率的なルート計画に役立つでしょう。
出典:料金プラン|TODOCUサポーター
配送ドライバーがよく使う配送ルートサービスは?
配送ドライバーは、業務内容や所属会社によって、さまざまなルートサービスを使い分けています。
アマゾンフレックスやヤマト運輸の委託ドライバーは、専用アプリで荷物情報をスキャンするだけです。
スキャンすると住所や氏名・会社名が自動入力され、最適な配送ルートが自動で組まれる仕組みになっています。
一方、自社ツールがない案件では、グーグルマップを基本に「配達NAVITIME」「GODOOR」「TODOCUサポーター」など配送専用アプリを併用するスタイルが一般的です。
これらのアプリは、ゼンリン住宅地図や時間帯管理、置き配メモ機能など、配送業務に特化した便利機能が豊富に搭載されています。
グーグルマップだけでは補えない細かなニーズに対応している点が特徴です。
どのサービスを使うかによって、ルートの効率や再配達の削減にも直結するため、業務内容に合ったアプリ選びが業務効率を左右するといえるでしょう。
配送ドライバーの転職ならハコボウズのキャリア相談◎
初めて配送業務に挑戦する方にとっては、そもそも配送先にたどり着くこと自体が一苦労です。
配送ルートの組み方次第で作業スピードや再配達の有無が大きく変わるため、ルート最適化は業務効率に直結します。
グーグルマップは無料で使える反面、初心者が自力で最短ルートを組むのは難しく、有料アプリの導入も費用面で悩ましいところです。
だからこそ、配送ドライバーにとって「ルートの選び方」だけでなく、「働き方そのものの見直し」が重要になります。
そんなときに頼りになるのが、軽貨物専門の求人サイト「ハコボウズ」のキャリア相談です。
配送業界を熟知したアドバイザーが未経験の方にも寄り添いながら、自分に合った働き方を一緒に考えてくれます。
また、配達だけでなく相談者のニーズに合わせて、トラックやタクシーなどさまざまなドライバー職を紹介できる点も強みです。
まずはLINE無料相談からスタートして、自分らしい働き方を見つけてみてはいかがでしょうか。